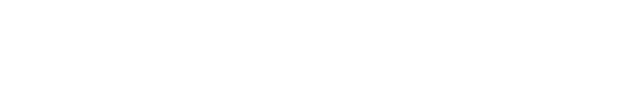医療法人からの施設を含めての独立承継について:リニューアル版(DSS:Q&A)
【医療法人からの施設を含めての独立承継について】
|
《解説》 クリニックの展開をする医療法人が増加している。 その一方、給与トラブルや分院院長の退職後、 人材が見つからず 閉院する医療機関もある。 医療機関を維持していく考えばかりではなくお互いに連携医療機関 としてクリニック展開を考えていくことも一つの方法といえる。 |
Q医療法人の分院院長をしているが、開院当初5年経過後にクリニックを
承継してもよい(譲渡)という契約を交わしています。
承継する(譲渡)とすれば、手続き等においてどのようなことに
注意すればよいでしょうか?
A、診療所の展開は、開設することは簡単であるが継続していくことは意外に難しい。
院長がクリニック運営に自信を持つことで「自分でも開業できる。」
と考えるようになるからである。
病院の院長や大学の教授等に就任することを除けば開業は
医師として大きな目標の一つともいえる。
開業することに関する勧誘も多い。以前とは異なって情報も多く
分院院長としてのリスクや安定に対する良い面には触れず、
独立開業すると「先生もっと儲かりますよ」「もっと給与をもらうべきですよ」
言われることが多く、開業におけるリスクに触れることは少ない。
実際、医療法人から施設を含めて独立する場合には、医療法人の医療機関としての
廃院日と個人クリニックとしての開院日が同日又は連続していなければ社会保険で遡及が
認められないことや開院時の保健所の監査日程等を注意しなければならない。
全ての手続きは、ゼロからのスタートとなるので生活保護や社会保険等に関する
加算の申請などうっかりすると継続して加算が取れなくなることもあるので
その点は事前の確認が重要である。
また労働保険や社会保険など医療法人と個人では異なる点もあるので
職員の待遇に関する問題についての確認も必要である。
また譲渡条件については、クリニック開設時の借入金やリース、職員の問題など
多くの打ち合わせしなければならない事項があるので十分に期間を
取る必要性がある。
基本的な打ち合わせ確認事項を挙げておく。
|
《確認事項》 ・ 譲渡金額の考え方 (内装や備品等減価償却後の残存価格等) ・ 借入金の処理 ・ リース機器の処理 ・ 職員への対応 (労働保険、社会保険等含む) ・ 賃貸契約に関する処理 ・ 在庫処理 |